山中渓温泉
山中渓(やまなかだに)は、江戸時代には紀州街道沿いに20余件の旅宿が建ち並ぶ宿場町として栄えました。また、街道と並行して流れる山中川には、古くから「川の傍らに冷泉が湧く」との言い伝えがあり、胃腸病、神経痛などに効験のある鉱泉(こうせん)が湧き出していました。
昭和5(1930)年、阪和電気鉄道が東和歌山駅まで延伸し、山中渓駅が開設されるのですが、その翌年の7月には、山中川の清流を臨む地に温泉旅館「ほととぎす」が開業しています。「ほととぎす」は、朱塗りのささやき橋を渡ると木々や石を配した庭園が広がり、後に当時としては珍しい奇石怪岩(きせきかいがん)を組立てた大岩窟(だいがんくつ)風呂「岩戸湯」を設け、建物も増築を重ねて、100畳と40畳の大宴会場をはじめ、40もの客室を数える大旅館へと成長していきます。
この「ほととぎす」の成功を契機として、趣向を凝(こ)らした温泉旅館が次々と建てられます。桜花満開の頃は京都清水寺の舞台の観(かん)があり、浴室からは紀泉アルプスや松林を展望できる「阪和館」。後ろに山、前の渓流(けいりゅう)には、朱色のみかえり橋が架かり、透き通ったお湯の「水晶(すいしょう)風呂」が自慢の「山中荘」。眺望絶佳(ちょうぼうぜっか)を誇り、広大な池での魚釣りやボート遊びが楽しめる、納涼には最高の「つるのや」。その名の通り、正面に極彩色(ごくさいしき)の竜宮(りゅうぐう)、左右に乙姫と浦島太郎を描いた「竜宮風呂」で客の目を楽しませ、また別館からは山中渓の全景を眺望することができた「元禄」。これらの旅館には、「ほととぎす小唄」、「山中荘音頭」などのPRソングもでき、最盛期には、芸者さんや仲居さんが赤い前掛けをして、山中渓駅前で温泉客を出迎えたとのことです。このように山中渓温泉は、昭和30年代には「大阪の奥座敷(おくざしき)」とまで言われ、温泉街は活況(かっきょう)を呈(てい)し、銀(ぎん)の峰(みね)ハイキングコースやテント村などでは、アウトドア・レジャーも盛んに行なわれていたようです。
春には桜、夏には納涼とアウトドア・レジャー、秋には紅葉と松茸、冬には温泉(いでゆ)と四季それぞれの魅力があり、休日には臨時のハイキング列車も運行するほどの賑(にぎ)わいを見せていた山中渓温泉街でしたが、「ほととぎす」では室戸(むろと)台風によりささやき橋が流され、建物などにも大きな被害がもたらされます。「山中荘」は、阪和自動車道の建設により消滅。「阪和館」も、府道拡張工事で道路用地となるなど、時代の流れにのみ込まれていきます。また一方では、松喰虫(まつしょくむし)による被害で赤松が枯れ、松茸も出なくなるなど、負(ふ)の連鎖(れんさ)により旅館街は廃(すた)れ、温泉郷には自然だけが残されました。しかし、近年、桜の植樹やハイキングコースの整備、ホタルやアユの放流など、その残された自然を活用しようとする活発な動きが見られ、さくら祭りやホタルの舞う里として親しまれています。
阪和電気鉄道;現在のJR西日本阪和線。
東和歌山駅:現在のJR和歌山駅。
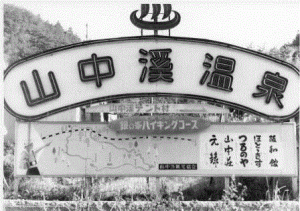
山中渓温泉の案内板
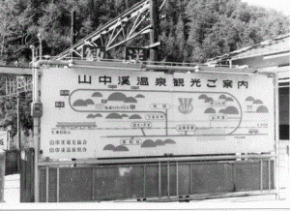
山中渓駅前の観光案内

「ほととぎす」と「阪和館」の入口
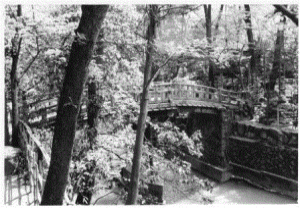
「ほととぎす」
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習部 生涯学習推進室 生涯学習推進担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4542
Eメール:s-gakusyuu@city.hannan.lg.jp






