コレラの流行
コレラは、激しい下痢や吐き気を起こす法定伝染病の一つで、日本では東南アジア帰りの旅行者などがしばしば現地で感染し、患者が発生しています。
江戸時代の文政5(1822)年、日本で最初にコレラが流行し、明治時代には数年ごとに大流行を繰り返し、明治時代の45年間の死者は全国で約37万人に上りました。
明治10(1877)年9月に横浜で、同じころ長崎でも入港した外国軍艦からコレラ患者が発生しました。この年は9月24日に西南戦争が終結し、召集されていた兵士が故郷に帰ることにより、日本中にコレラ菌を蔓延(まんえん)させました。この流行では1万3816人が発症し、そのうちの8027人が死亡しています(死亡率約60%)。次いで明治12(1879)年、明治19(1886)年にも大流行があり、感染者数は15万5923人、死者10万8405人(死亡率約70%)にも達しています。
この頃のコレラ対策は、患者の早期発見と隔離(かくり)、または「石炭酸(せきたんさん)」という消毒薬を散布するかのいずれかしかありませんでした。
当時の阪南市域でもコレラは猛威(もうい)を振るいました。史料によると新村(しむら)では、明治12年の流行時に1人、明治19年には10人もの死者が出たとあり、各村々では、予防手当を厚くすることを申し合わせ、「石炭酸」を各家に漏れなく配布しました。また、各村ごとに隔離病舎を設け、布団、大瓶(おおがめ)、便器、屏風(びょうぶ)を備え付け、看護人を1人置いたことが記されています。
このように江戸・明治時代には脅威であったコレラも、医療体制の発展により適切な治療が行われ、今日ではその死亡はほとんどなくなりました。
新村:現在の新町
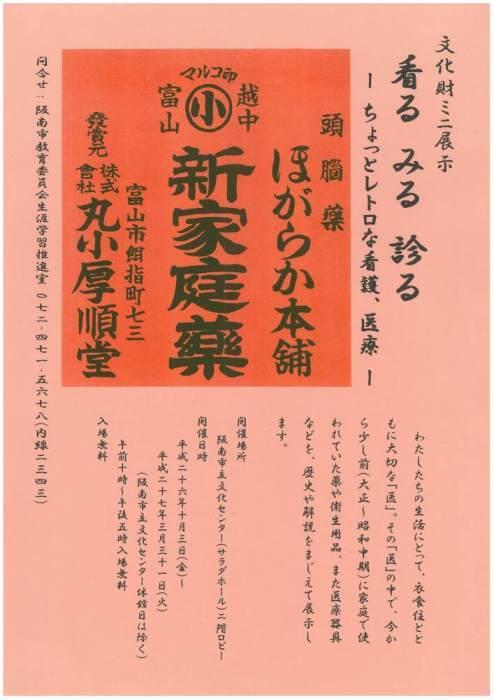
この記事に関するお問い合わせ先
生涯学習部 生涯学習推進室 生涯学習推進担当
〒599-0292
大阪府阪南市尾崎町35-1
電話:072-489-4542
Eメール:s-gakusyuu@city.hannan.lg.jp






